�ёы��j
���̂Q�@ (29 - 58��)�@/�@�S347���⍑���Êُ���
�i�c�@�V�V�q�i���A�⍑�������j�@�⍑�ό�����1953�N2�����s
����@�F�@�y�[�W�k���}�������Ɗg��y�[�W�ɂȂ藼�[�������ƕł߂���ł��B�g���A�g�O���ӂ������ƕ��܂��B
-
��l�́@���̗��j�Ƌёы�
��A�ӊ��̒�����ؑ����܂�
 �P�y�[�W�@�Q�X
�P�y�[�W�@�Q�X
-
���m���������{�ɓ���O�A�]�ˎ���܂œ��{�̋��͑S�Ėؑ��ł������B
��O�́A���i11�N(1634�N�j����Ŏx�ߑm�@�肪�A�������̃A�[�`�^�Α����A�ʏ̊ዾ�������B
�܂������ł͎�������A���������̉e���ŐΑ��A�[�`�����˂����Ă����B
 �P�y�[�W�@�R�O
�P�y�[�W�@�R�O
-
��������ȍ~�̒뉀�ɂ͍H�|�i�Ƃ��āA�Α��A�[�`�����˂����Ă��������p�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�
 �P�y�[�W�@�R�P
�P�y�[�W�@�R�P
-
�L�b�G�g�����ɒz�邵�Ďs���ɑ����̋����˂������A�F�A�ؑ��̌����ł���B
����ƍN���]�˂ɖ��{���J���ē��{���ȂǑ����̋����˂������A�������ؑ��̌����ł���B
��A�ؑ���������A�S���A�|���ƂȂ�܂�
�����ɂȂ��āA�p���l�Z�t�ɂ��S�������X�ɑ���ꂽ �P�y�[�W�@�R�Q
�P�y�[�W�@�R�Q
-
�Α��A�[�`�������X����ꂽ���A�֓���k�ЂŔ�Q�ɂ����Ă���B�S���͐���ɑ���ꂽ�B
 �P�y�[�W�@�R�R
�P�y�[�W�@�R�R
-
���[���b�p�ɂ����Ă͐Α��A�[�`�������������Ă���B�ނ̌Œ�ɃZ�����g��ΊD���g���Ă���B
�킪���ł͐ނ̌Œ�Ɏ��g���Ă���B����̐��@�͂킪���Ǝ��ł��蓒��ƕ����ɋL�ڂ���Ă���B
���[���b�p�ł͑����̐Α��A�[�`�����c���Ă��邪�A�ŋ߂͓S����|���ɕς�����B
 �P�y�[�W�@�R�S
�P�y�[�W�@�R�S
-
�O�A���Č×��̑g���ؑ����Ƌёы�
 �P�y�[�W�@�R�T
�P�y�[�W�@�R�T
-
�ёы��n�݂����100�N���1758�N�A���[���b�p�̃C�^���A�Ńg���X�\�����x�[�X�Ƀ��C����ɁA�P�P�X���̌��Ԃ�����ؑ������˂���ꂽ�B
 �P�y�[�W�@�R�U
�P�y�[�W�@�R�U
-
�k�Ă̊J��͑����̖؋�������ꂽ�B���������Ė؍ނ̕��H��h���H�v��������A���ԂP�O�O������ؑ���������ꂽ
 �P�y�[�W�@�R�V
�P�y�[�W�@�R�V
-
�l�A���Ėؑ����̃A�[�`�^�\��
�g���X�\�������x�[�X�ɂȂ��Ă���B �P�y�[�W�@�R�W
�P�y�[�W�@�R�W
-
���Ăł͓S�������g���X�\������{�ł���B
�܁A�䍑�ؑ����̔����y�є��B
 �P�y�[�W�@�R�X
�P�y�[�W�@�R�X
-
�ŏ��́A���݊Ԃɒ��i���j���������A�����ɔ�y����킹��ȈՂȂ��̂ł���i��18�}�P�j�B
�������A�[���k�J��}�����܂����ꍇ�͒������Ă��Ȃ��B�����݂���ˏo�������19�}�̈Ă�����B �Α���A�[�`�����20�}�Ɏ����B�܂��A��21�}�̂悤�Ɏ߂̕��ނŎx���邱�Ƃ����� �P�y�[�W�@�S�O
�P�y�[�W�@�S�O
-
�ˏo����ƃA�[�`���̒�����g�ݍ��킹����24�}�͒����X�p���̋����\�ł���
 �P�y�[�W�@�S�P
�P�y�[�W�@�S�P
-
��24�}�̃X�p�����X�ɐL���ɂ͑�25�}�̂悤�ɁA���肾�����㕔�̗������Ȃ������`��ɂ����A���ꂪ�ёы��̋N���ł͂Ȃ����ƍl����B
 �P�y�[�W�@�S�Q
�P�y�[�W�@�S�Q
-
����Ƃ��ẮA�b�B�̉������͂��ߐM�B�̎R�ԕ��Ɍ���B��28�}�A29�}�̋��B��30�}�A��31�}�̓C���h�l�V�A�̃W�������ɒ|��������B
��33�}�̔@�����́A����˂������k�J�ɉ˂������{���������34�}�͋ёы��̍\���ɂɂĂ���
 �P�y�[�W�@�S�R
�P�y�[�W�@�S�R
-
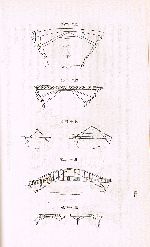 �P�y�[�W�@�S�S
�P�y�[�W�@�S�S
-
 �P�y�[�W�@�S�T
�P�y�[�W�@�S�T
-
�Z�A�䍑�뉀�p�ƃA�[�`�^�؋��̊W
�z��p�̎w�쏑�u�Αg�������d�_�`�v�ɂ͂Q�C�R����A�g�o���������͒z�R�̊ԂŒ���łĂȂ����ɉ˂���B �P�y�[�W�@�S�U
�P�y�[�W�@�S�U
-
���C���́A�J��[�����ɂ���A�_�ы��܂��͖ؑ]���Ƃ��Ăіؑ]�H��2�ӏ��������B���̂悤�ȑ����Z�p���ёы����c�̎��ɎQ�l�ɂȂ����\���͂���B
 �P�y�[�W�@�S�V
�P�y�[�W�@�S�V
-
�������A�⍑�˂ɂ͒뉀���̉Ɛb�͂��Ȃ������̂Ō������x�ł���B
���A���ċy�щ䍑�̋��̒ė���������Ƒ����P
 �P�y�[�W�@�S�W
�P�y�[�W�@�S�W
-
����4�N(1807�N�j�A�]�˂̉i�㋴���[�씪���{�̍�ŋ������܂�Ď��ҁE������1000���̎��̂��������B
�֓���k�Ђł͑����̋�����Q�����B���ˑ䕗�ȂǂŖ��\�L�̍^�����N���苴�r�����ꂽ�B
 �P�y�[�W�@�S�X
�P�y�[�W�@�S�X
-
1879�N�A�X�R�b�g�����h�ŕb���R�T���̂Ȃ��ŗ��q��Ԃ���Ƃ��S��������鎖�̂��N�����B
 �P�y�[�W�@�T�O
�P�y�[�W�@�T�O
-
1902�N�A�J�i�_�̃Z���g���[�����X��ɉ˂��Ă����H�����̍|�S�������������B
 �P�y�[�W�@�T�P
�P�y�[�W�@�T�P
-
 �P�y�[�W�@�T�Q
�P�y�[�W�@�T�Q
-
1940�N�A�A�����J�ŋ��̌Œ�U���������Ƌ��U���ď㉺���E�ɑ傫���U�����ĉ�ꂽ�B
 �P�y�[�W�@�T�R
�P�y�[�W�@�T�R
-
���A�x�ߌÑ�l�̋��Ɋւ���\�z
 �P�y�[�W�@�T�S
�P�y�[�W�@�T�S
-
 �P�y�[�W�@�T�T
�P�y�[�W�@�T�T
-
 �P�y�[�W�@�T�U
�P�y�[�W�@�T�U
-
 �P�y�[�W�@�T�V
�P�y�[�W�@�T�V
-
 �P�y�[�W�@�T�W
�P�y�[�W�@�T�W


