錦帯橋の由来及び其構造
岩国中央図書館所蔵岩国市横山 財団法人 岩国保勝會 1950年1月発行
注 出版後50年経過して著作権は消滅しているため全文を掲示します
要旨
本冊子が書かれたのは1950年1月で、この年の9月キジヤ台風で創建以来276年ぶりに橋脚の一部が崩れた。
当時、国会で錦帯橋を国宝認定する機運が盛り上がっていた。以下に要旨を述べる
小冊子(参考文献)
曲がった橋の理由:
江戸時代初期、川を渡る手段は渡し船・柴橋・土橋だったが錦川では洪水のたびに流された。 吉川第三代藩主広嘉公が腐心の末、アーチ橋と橋脚構築法に工夫を凝らして創設した。276年間、激しい洪水に耐え今日に至っている-
創案の動機:
吉川第三代藩主広嘉公は、歴代徳川将軍・幕府指導部は聡明で内乱の憂いは少ないと判断し内政に舵をきった。 地元では、柿餅が膨れる姿をみてヒントにしたとか、明の亡命僧侶独立から中国の石造アーチ橋の話を聞いて思いついたとかの逸話が残っている。 -
世界的に稀な奇構:
江戸時代初期に落ちない橋を実現するために英知と努力を結集した結果である、木材の架橋を支えるため上流・下流20間〜60間に渡り河床の下に3層の石を敷き、最下位部下には数万本の生松の柱打ち込みなど人力だけでこれだけの大工事をを行った例は少ない。 聞けば聞くほど先人の努力に感嘆する。 -
石積みは近江坂本の穴太衆より伝授:
延宝元年の錦帯橋は橋脚が崩れたので、近江の穴太衆に指導を願ったが、当時の築城石積み技術は軍事機密で命がけだった。 -
錦帯橋の真価は木造橋より河床下の埋没工事:
洪水に負けない仕掛けは橋脚の下にあり、目には見えないが大努力がある。 (注 最近地震や大雨による堤防決壊があるが、堤防下の重厚な基礎工事こそ重要だと江戸時代初期に気付いている) -
橋脚の先端は船の先端のように水を切る菱形になっている:
激流が橋脚に当たると後ろ尾の部分に渦巻きができて、小石を巻き上げ、橋脚内部が空洞になることがある。 先端が尖り真ん中付近が緩やかに丸くなる大型船舶の船底と同じ形状であり、現在の流体力学に近い合理的な形状をしている。 -
橋脚の根元には生松の杭を打ち石垣にしている:
橋脚の根元には沈下防止のため生松の杭をひし形状に組み、内部に栗石を詰め、周囲は石垣にしている。 -
河床下に三層の石畳:
橋脚の河床に埋まる前後左右が洪水で洗い流されると橋脚が根底から崩落する危険があるので橋脚の上流下流に三重の敷石が施している。 一層目と二層目は見えないが、最上部の第3層部は一部が石畳として見えている。
最下部、一層目の敷石:
川の両岸間、橋脚の上流下流60間に生松の乱杭数万本を打ち込み、その杭の間に大石、中石、小石を取り混ぜて詰め込んだ。 記録によるとこれには河船で延べ数万回運搬したと記されている。人力による大工事である。
中敷の二層目敷石:
川の両岸間、橋脚の上流下流40間に、荒石を混ぜ合わせて敷きこんだ
最上部、一層目の敷石:
川の両岸間、橋脚の上流下流20間に、石垣を積み上げる迫持構造で敷きこんだ
-
橋の重みを橋脚上の割石で両方から受けている:
錦帯橋の構造は、両端から玉すだれのように延びて互いに支えあっているので、上に重いものが乗るほど引きしまる。
 架橋構造は岩国市錦帯橋課のホームページに詳しく解説されています
架橋構造は岩国市錦帯橋課のホームページに詳しく解説されています
-
270年前の創建時のまま引き継いでいる:
橋脚と河床下の石畳等の基礎部分は創建時のままである。架橋部は木製で度々架け替えられている其構造は創建時のままである
錦帯橋は公道である:
明治・大正時代錦帯橋は国道であったが、国道2号線が山側に開通してから市道になった。文部省により名勝指定されているが道路維持管理費用は山口県から出ている
国の保護建造物:
錦帯橋は国の「史跡名勝天然記念物法」により、「名勝」として文部省の管理下にある。橋だけでなく上流下流の広範囲が保護管理対象であり、 錦帯橋は人以外通行できない。また、河に錨を下ろしたり河底の敷石・砂利の採取が禁止されている。 -
錦帯橋を国宝に:
昭和7年より錦帯橋を国宝にする問題が文部省の懸案になっていた。国宝実施の場合は交通を禁じるため、上流または下流に近代技術で平坦な橋を造る必要があると考えられていた。 国会でも錦帯橋を国宝にする提案がなされ機運が高まってきた。
(注 残念なことに此の年の秋9月、キジヤ台風で橋脚は一部崩れ、木造の架橋は流失して国宝は棚上げになった。その後、錦帯橋車両通行禁止と上流に近代技術で平坦な橋は造られた)
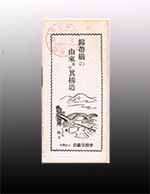

表紙


単ページ 1


単ページ 2


単ページ 3


単ページ 4


単ページ 5


単ページ 6


単ページ 7


単ページ 8


単ページ 9
